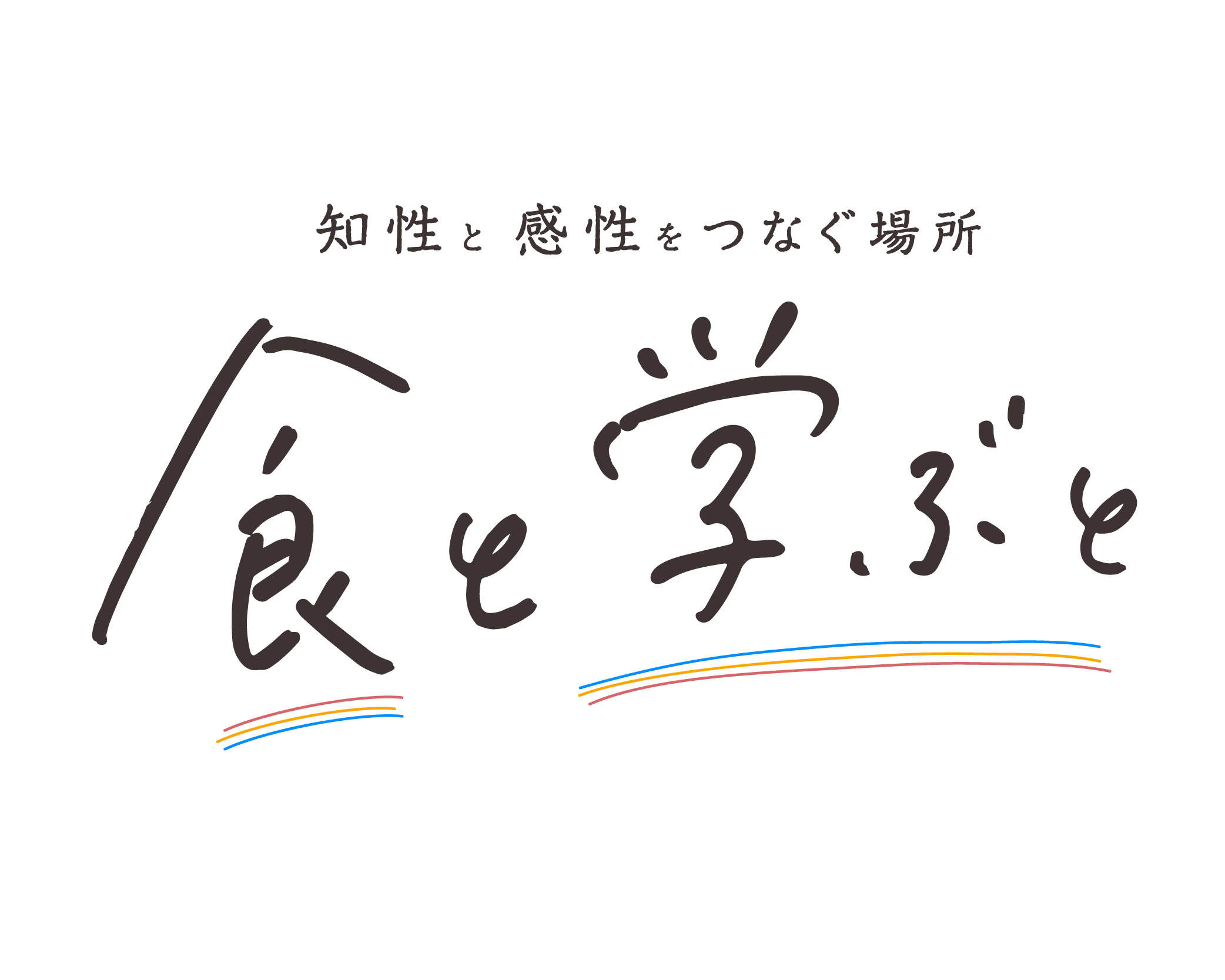子どもに料理を教えるのは危ない?年齢別で安心なステップアップ方法

「料理に興味があるみたいだけど、本当にやらせて大丈夫かな…?」そんな迷いを感じたことのあるママは多いのではないでしょうか。子どもにとって料理は魅力的な体験。でもその一方で、親としては“危ないこと”がたくさん思い浮かんでしまうものです。
包丁で指を切ってしまうのでは?火傷をしないだろうか?熱湯やコンロの火、油のはね…。料理には想像するだけでヒヤッとする場面が多く、最初の一歩を踏み出すのをためらってしまうのも無理はありません。
この記事では、年齢別にできることを詳しくご紹介していきます。
子どもの年齢ごとに違う「できること・危ないこと」

子どもに料理を教えるとき、「子どもって何歳でなにができるの?」という不安はつきもの。発達段階に応じて、安心して任せられる作業と、まだ注意が必要な作業があります。家庭で無理なくステップアップするために、子どもはどんなことができるのか、年齢ごとの特徴を見ていきましょう。
3〜4歳:料理ごっこからスタート
この時期の子どもには、火や刃物を使わない「まねっこ料理」がおすすめです。たとえば、
- レタスをちぎる
- おにぎりを丸める
- ピーマンの種を取る
といった作業は安全で、達成感も得られやすいです。子ども用のエプロンや調理道具を準備すると、さらにやる気がアップします。
5〜6歳:道具に触れはじめるタイミング
好奇心が高まり、「本物の料理をしてみたい!」という意欲が育ってきます。ここでは、
- 子ども用の包丁でやわらかい野菜を切る
- ピーラーでキュウリやニンジンの皮をむく
- ゆで卵の殻をむく
などが可能になります。ただし、力加減や手の動かし方に不安があるため、必ず大人が手を添えて教えるようにしましょう。
小学生低学年:加熱調理にチャレンジ
火や電子レンジを使った調理に挑戦できるようになる時期です。たとえば、
- トースターでパンを焼く
- ホットケーキを焼く
- インスタントスープを作る
などの「見た目の変化が楽しい」工程を取り入れると、達成感と好奇心がどんどん育ちます。火の扱いには引き続き注意を払いましょう。
小学生高学年:本格調理に一歩近づく
包丁や火の扱いにも慣れてきて、大人と同じような作業ができるようになります。ここでは、
- コンロで炒め物を作る
- 出汁をとる
- 包丁で細かく刻む
といった応用的な調理も可能です。ただし、「慣れた頃こそ要注意」。油跳ねや火加減ミスなど、経験が増えるからこそ見落としがちな危険もあります。
安心して子供が料理できるための環境づくり

料理は楽しい反面、思わぬケガにつながる危険もあります。子どもが安心してチャレンジできるようにするには、事前の環境づくりが欠かせません。ここでは、安全に料理を学べる空間を整えるためのヒントをご紹介します。
高さと動線を見直す
子どもの背丈に合った作業台や踏み台を用意すると、無理な姿勢にならずにすみます。手元が安定することで、包丁や調理器具の扱いもスムーズになります。
また、キッチン内の動線も重要です。熱い鍋や食器、コード類などにつまずかないよう、床の上や作業まわりをすっきりさせておきましょう。
危険な道具の管理を徹底する
包丁、火、油、電子レンジなど、事故につながりやすいものは子どもの手が届かない場所に収納したり、使うときには必ずそばに大人が付き添うようにします。
とくに、包丁置き方、向きには注意が必要です。また、コンロ周りの拭き忘れによる引火には注意しましょう。
子ども専用の安全な道具を使う
子ども用包丁、滑り止め付きまな板、手が届きやすい軽量なボウルなど、年齢に応じた道具をそろえることで「できた!」という体験を増やせます。
安全に配慮された道具は、子どもの「やってみたい」という気持ちを支える大切なパートナーになります。
料理中の“ヒヤリ”を防ぐ!子どもへの声かけと見守り方
どれだけ準備を整えても、子どもの料理には思わぬ“ヒヤリ”とする瞬間がつきもの。だからこそ、日常的な声かけと大人の見守りがとても大切です。無理なく楽しく料理できるように、安心を支える工夫を取り入れてみましょう。
「危ない」より「どうする?」の声かけに変えてみる
つい「危ないよ!」と制止したくなりますが、それでは子どもが怖がってしまうことも。「包丁を使うときは、手は猫の手にしてみようね」「熱いから、大人と一緒にやろうね」と、具体的な行動を促す言葉に置き換えてみましょう。
こうした前向きな声かけは、子どもの主体性を育てながら安全意識を高める助けになります。
手を出すタイミングを見極める
見ていると手を出したくなる場面も多いですが、「あと少しでできるかも」というところで待つことも大切。子どもが困っていそうなときには、「どうしたらいいかな?」と声をかけて、一緒に考える時間に変えていきます。
大人がすぐに助けてしまうと、子どもは「失敗しちゃいけない」と感じてしまうことも。ゆっくりと失敗も経験させることで、料理への自信が育まれていきます。
褒めるのは「結果」より「姿勢」
うまくできたときはもちろん、「真剣に包丁を持っていたね」「最後までがんばったね」といった、プロセスを認める言葉がけを心がけてみてください。
結果ではなく努力や集中に目を向けることで、子どもは安心して挑戦できるようになります。
子どもと料理することの本当の意味とは

「料理=食事の準備」だけじゃない。子どもとキッチンに立つことは、栄養や調理技術以上に、心や人間性を育む大切な時間になります。ここでは、料理を通じて育まれる力について掘り下げてみましょう。
自分の手で作ることで「食べること」が特別になる
料理の工程に関わると、子どもは「食材が料理になる過程」にワクワクします。そして、自分で作ったものには自然と愛着がわき、「残さず食べたい」という気持ちが芽生えるものです。
・偏食が減った
・苦手な野菜にチャレンジできた
そんな声もよく聞かれます。
生活力と「段取り力」が自然と身につく
材料の準備、加熱のタイミング、盛り付けの順番…。料理には“段取り”がつきものです。子どもはこの中で「順番を考える力」や「効率よく動く工夫」を自然と体で覚えていきます。
これらは、将来的に勉強や時間管理にもつながる力。料理は日常の中で無理なく「生きる力」を養う場でもあります。
親子で並ぶ“横の関係”が信頼を育てる
料理中は、指導するというより“いっしょにやる”時間。親が手を出しすぎず、子どもの工夫を見守ることで、「信じてもらえた」という感覚が育ちます。
親子の会話も自然と増え、学校では聞けない気持ちがふとこぼれることも。料理の時間は、親子が“並んで歩く”関係を築くきっかけになります。
「子どもに料理を教えるのは危ない」を乗り越えるには

「最初からうまくできなくて当然」という視点を持つことが、親の心にも余裕をもたらします。うまくやらせようとするのではなく、試行錯誤する場を用意することが大切です。
失敗を叱るよりも、挑戦したことを認める
料理の最中にこぼしたり、切った野菜の形が不揃いだったり。そんな失敗は、子どもにとって「やってみた証」です。
大人が見ていると、「あっ!」と声を出したくなる瞬間もありますが、その前に「やってみたね」「ここまで自分でやれたね」と声をかけることで、子どもの自信は確実に育ちます。
叱るのではなく、挑戦に対して拍手を送る。それが、料理を楽しい体験に変える一歩です。
一緒に笑って片づけることで、家事への抵抗感を減らす
料理の後片づけは、子どもにとって一番面倒に感じるかもしれません。でも、ここを親子で「楽しい時間」に変える工夫もできます。
「どっちが早くスポンジできれいにできるかな?」とゲーム感覚にしたり、「お皿の泡がキラキラしてるね」と観察を楽しんだり。
“家事=大変”という印象を少しでもやわらげることで、「またやってみたい」という気持ちを自然と育てていくことができます。
まとめ:子どもが安全に料理と関われる“ちょうどいい距離”を見つけよう
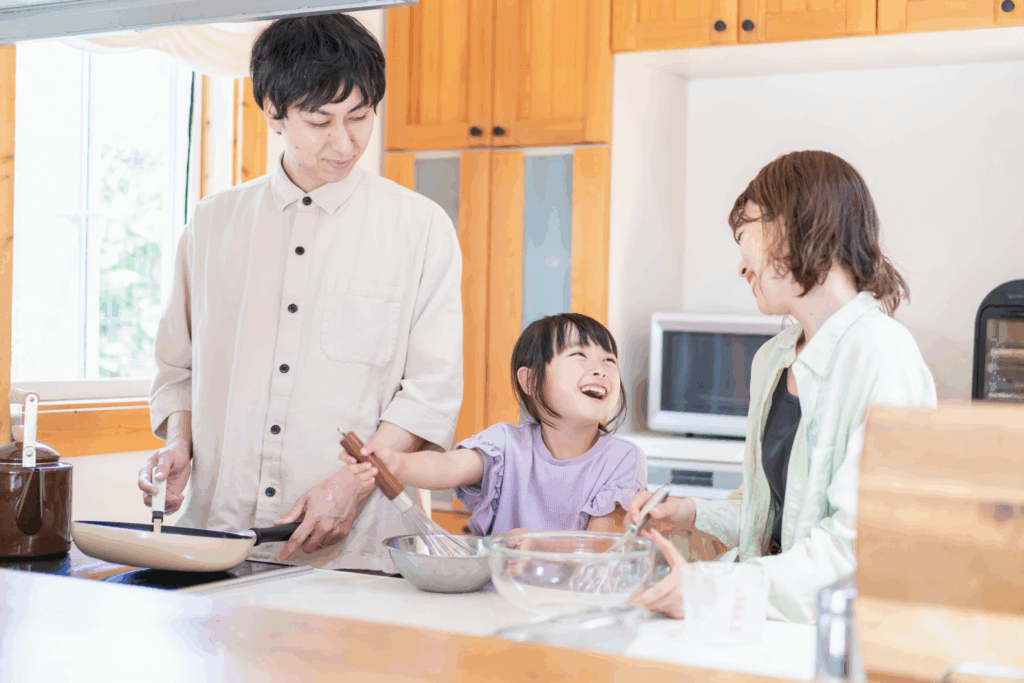
料理を教えるうえで大切なのは、「完璧にできるようにすること」ではありません。子どもが安心して挑戦できる環境をつくりながら、少しずつ経験を重ねていくことです。
いきなりすべてを任せるのではなく、「今日は野菜を洗うだけ」「次はおにぎりを握る」と段階を踏むことで、無理のないステップアップが可能になります。
子どもが自分のペースで楽しめるように、やる内容や関わり方を調整する“ちょうどいい距離”を見つけていきましょう。
料理には、手順を守る力、危険を回避する力、自分で工夫する力など、生きるうえで大切な力が詰まっています。
だからこそ、「やらせない」のではなく、「一緒に学ぶ」というスタンスが必要です。親も子も、少しずつ経験を積みながら“安全に育つ力”を育てていく。それが、料理という家事を通じて得られる最大の学びかもしれません。
子どもが安全に、そして積極的にチャレンジするためには、周囲の大人の働きかけが大きなポイントです。
【キッズ食育トレーナー】の学びの中にはそういったこどもの「やってみたい!」を応援できる学びがたくさん。
・もっと子どもと楽しく料理が出来たらいいのにな。
・怪我が心配でなかなか任せられない
・子どもとキッチンで料理が出来たら楽しいだろうなあ。
そんな想いを現実に変えてくれるヒントが沢山!まずは体験講座に参加してみてはいかがでしょうか?