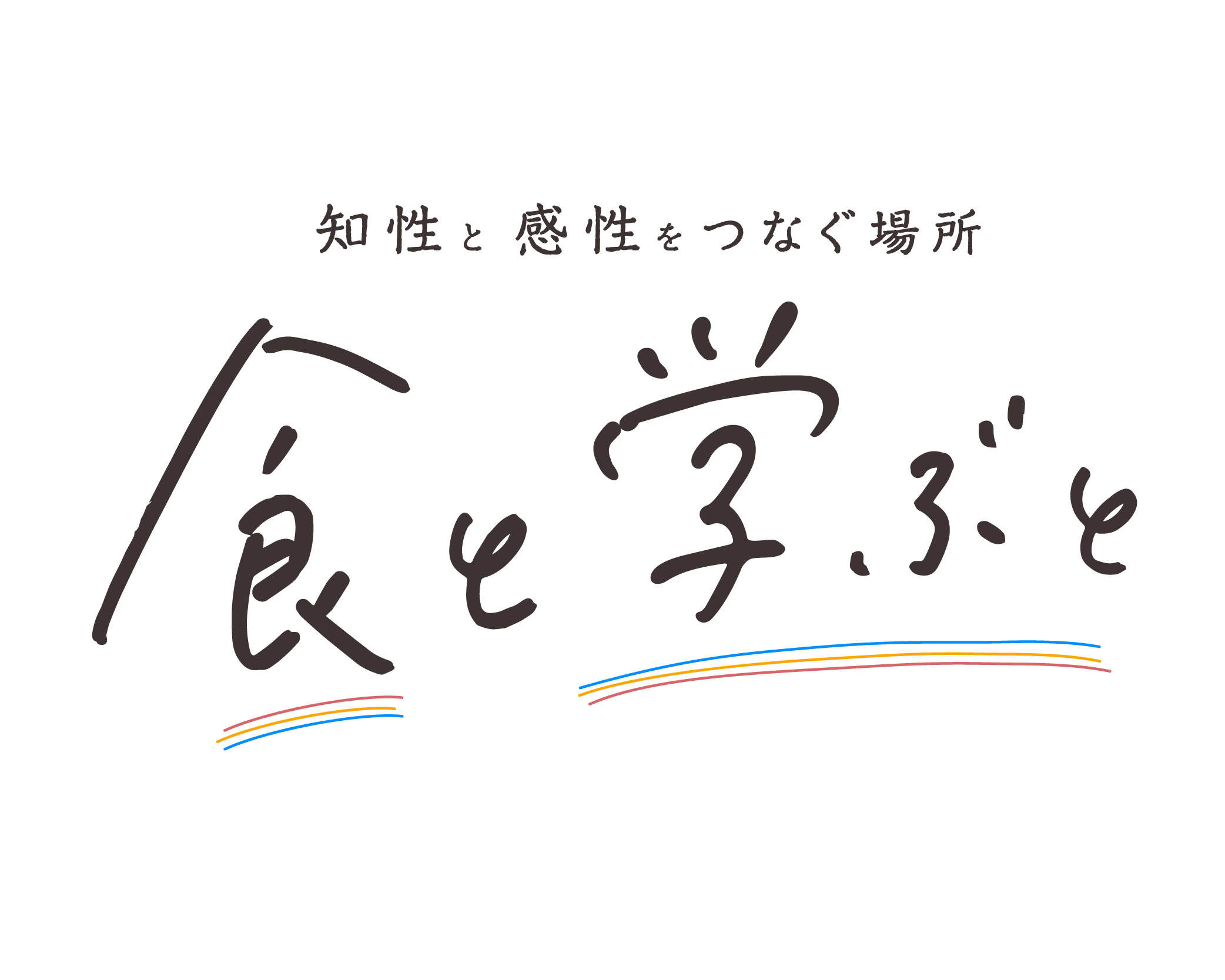子どもが包丁を使う時に気をつけたいこと。家庭で守りたい安全ルールと練習のステップ

「包丁はまだ危ないかな…」「興味はあるけど、ケガをさせたらどうしよう」
子どもに料理を教えたいと思いながらも、包丁となると不安になる方は多いはず。
でも、包丁は“危ないもの”ではなく、“安全に使えるようになる道具”と考えると、関わり方が変わってきます。
大切なのは、使い方を段階的に身につけられるよう、親子でルールを育てていくこと。
このページでは、家庭でできる安全対策や年齢別のステップアップ方法をご紹介します。
包丁を使う前に大切なこと|子どもに伝えたい“安全のルール”

包丁を使わせるタイミングに迷う方も多いですが、実は始める前の“心の準備”こそがとても大切です。子どもが安心して台所に立てるように、まずは一緒にルールを育てていきましょう。
包丁を使う前に確認したい「5つの約束」
包丁は、正しく使えば料理の楽しさを広げてくれる便利な道具です。でもその一方で、扱いを間違えればケガにつながることもあるため、「なんとなく持たせる」のではなく、しっかりとした“入口”を用意してあげることが大切です。
家庭で包丁を使う前に、以下のような約束を共有しておくとスムーズです。
- 包丁は、大人と一緒に使う
- 手をきれいに洗ってから始める
- 刃ではなく、柄(え)をしっかり持つ
- 切るときは、ふざけずに集中する
- 使い終わったら、すぐに所定の場所に戻す
この約束は、紙に書いて冷蔵庫やキッチンの壁に貼っておくと、子ども自身が視覚的にも確認しやすくなります。
また「間違えたら怒られる」ではなく、「どうすればもっと安全かな?」と一緒に考えるスタンスが大切です。
大人の焦りや不安が伝わってしまうと、子どもも緊張してしまいます。
包丁を手に取る前に、「安全に楽しく料理をするって、どういうことだろう?」を話す時間をもつことで、子どもの主体性も育っていきます。
年齢別に考える、包丁練習のステップと選び方

「そろそろ包丁を使って料理ができるかな?」と思ったとき、年齢ごとにどんな準備が必要か悩む方は多いものです。でも大切なのは、「何歳だからこれをやる」ではなく、その子自身の様子やペースに合わせて、少しずつ段階を踏んでいくこと。
ここでは、年齢別に包丁を使う練習の進め方と注意したいポイントをご紹介します。
3〜4歳|姿勢と環境づくりから始める
この時期の子どもは、手先の力や集中力にまだばらつきがあり、いきなり包丁を使うのは不安という方も多いでしょう。でも、「やってみたい!」という気持ちはとても豊かです。
まずは安全に立てる場所を用意することから。踏み台や滑り止めのマットを活用して、キッチンでの立ち位置を整えましょう。椅子に座って行う方法でもかまいません。
包丁を使う前に、バナナや豆腐など、押し切りできる柔らかい食材で「切る」感覚を体験するのもおすすめ。包丁の代わりにカード型のヘラを使うのもよいステップです。
5〜6歳|子ども用包丁での練習をスタート
この頃になると、子ども用の包丁(軽くて刃先が丸いもの)を導入できるようになります。ただし、いきなり「野菜を切ってみよう!」ではなく、まずは包丁に慣れることから始めましょう。
・包丁を持ってみる
・包丁の置き方を知る
・どこで切れるのか?どこを持つのか?を知る
こうした動作を一緒にゆっくり確認していくことが大切です。
また、切るときの「猫の手」や「添える手」などの基本的な動作も、できる範囲で少しずつ教えていきましょう。何より、「失敗しても怒られない環境」が、子どもの自信と意欲につながります。
小学生以降|目的を持って実践にステップアップ
小学生になったら、少しずつ実践の場を増やしていきましょう。ここで大切なのはあくまで「子ども」であることは忘れないこと。子ども用の包丁を使うのがオススメです。
このとき意識したいのは、「今日はサラダ担当ね」のように、役割を伝えて任せること。
自分が食卓に貢献しているという実感が、やる気と責任感を育てていきます。
また、包丁を使い終わったあとの洗い方や収納方法、刃の向きなども、一緒に学んでいけると安心です。調理の前後の所作も含めて、「包丁とつきあう力」を養っていくイメージです。
子どもが包丁でケガをしないための“環境づくり”

包丁を使う練習を始めるとき、一番大切なのは「安心して集中できる環境」を用意することです。これは、子どもだけでなく見守る大人にとっても、大きな安心材料になります。
作業台の高さを子どもに合わせる
大人と同じ高さのキッチンでは、子どもは腕を無理に上げて作業することになり、バランスを崩しやすくなります。踏み台や専用のキッチンステップを使って、作業面が子どものおへそ〜胸の高さになるように調整してあげましょう。
身体の安定がとれていると、自然と包丁の動きも安定していきます。
包丁とまな板は専用のものを
子ども専用の包丁を用意したら、まな板もなるべく滑りにくい素材で、小さめのものを選ぶと使いやすくなります。
まな板の下に濡れふきんや滑り止めシートを敷くと、さらに安心です。
「自分専用の道具がある」ということは、子どものやる気にもつながります。
作業の“時間”をあらかじめ区切っておく
集中力が続かない年齢では、長時間キッチンに立つのは疲れてしまうこともあります。
「今日は5分だけにしようか」「3切れだけ切ってもらおうか」と、あらかじめゴールを決めておくと、親も子も気持ちがラクになります。
途中で飽きてしまったり、ぐずってしまっても大丈夫。
「やりたくない」と言える雰囲気もまた、子どもの安心感につながります。
子どもと包丁を使うときの約束ごとと声かけ
包丁を使うときには、「やり方」だけでなく「気持ちの準備」がとても大切です。怖がりすぎず、でも油断しすぎない。そのちょうどいいバランスを親子で育てていきましょう。
声かけは「できる・できない」ではなく「どう使うか」に注目して
「危ないからやめて!」という言葉は、つい口から出てしまいがちですが、子どもの自信を削いでしまうこともあります。
たとえばこんな風に言い換えるだけで、ずっと安心感のある雰囲気になります。
- 「にんじんが動かないように手をこうしてみようか」
- 「猫の手にすると切りやすいよ」
- 「ゆっくりでいいよ、見てるからね」
子どもは、大人の声や表情から「自分を信じてもらえているか」を敏感に感じ取ります。
上手に切れたときはもちろん、手を止めて考えたり、慎重になったときにも「今のやり方、よかったね」と声をかけてあげてください。
料理は“作ること”だけでなく、“関わること”そのものが学びの時間です。包丁を使うときも、正解を求めすぎずに「今この子が、どうやって料理と向き合っているか」を一緒に感じてみましょう。
まとめ:包丁は危険な道具。でも“安全に使える力”は育てられる

包丁は確かに、子どもにとって危険を伴う道具です。だからこそ、使ってもらっていいものかどうか、悩む親御さんの気持ちはとてもよくわかります。
でも実は、包丁を「使わせない」ことで安全を守るだけではなく、あえて使うことにより、「安全に使える力」を育てることも選択肢のひとつです。
大切なのは、無理をせず、年齢や発達段階に合わせて少しずつ経験を積んでいくこと。最初は道具に触れるだけでもOK。子ども用の包丁を使ったり、やわらかい食材から始めたりと、段階的なステップを踏んでいけば、子ども自身の「できた!」という自信にもつながります。
失敗しても叱らず、「一緒に考えてみようか」と声をかけられる関係性があることで、料理の時間が親子の信頼を深める時間にも変わります。
包丁は“使えるようになること”そのものが目標ではありません。子どもが自分の手を動かし、食と関わりながら、自分の命を守る力を身につけていく――そんな視点を持つと、日々の台所がちょっと違って見えてくるかもしれません。
チャレンジすることで新しい力を身につける機会に。
「やらない」選択は、子どもを危険から守るためには時に大切なことです。ですが、一歩踏み出してやってみることで新しい発見や、新たな気づきを得ることが出来るかもしれません。
【キッズ食育トレーナー】の学びの中にはそういったこどもの「やってみたい!」を応援できる学びがたくさん。
・もっと子どもと楽しく料理が出来たらいいのにな。
・怪我が心配でなかなか任せられない
・子どもとキッチンで料理が出来たら楽しいだろうなあ。
そんな想いを現実に変えてくれるヒントが沢山!まずは体験講座に参加してみてはいかがでしょうか?
体験講座のご案内はこちら→→キッズ食育体験講座