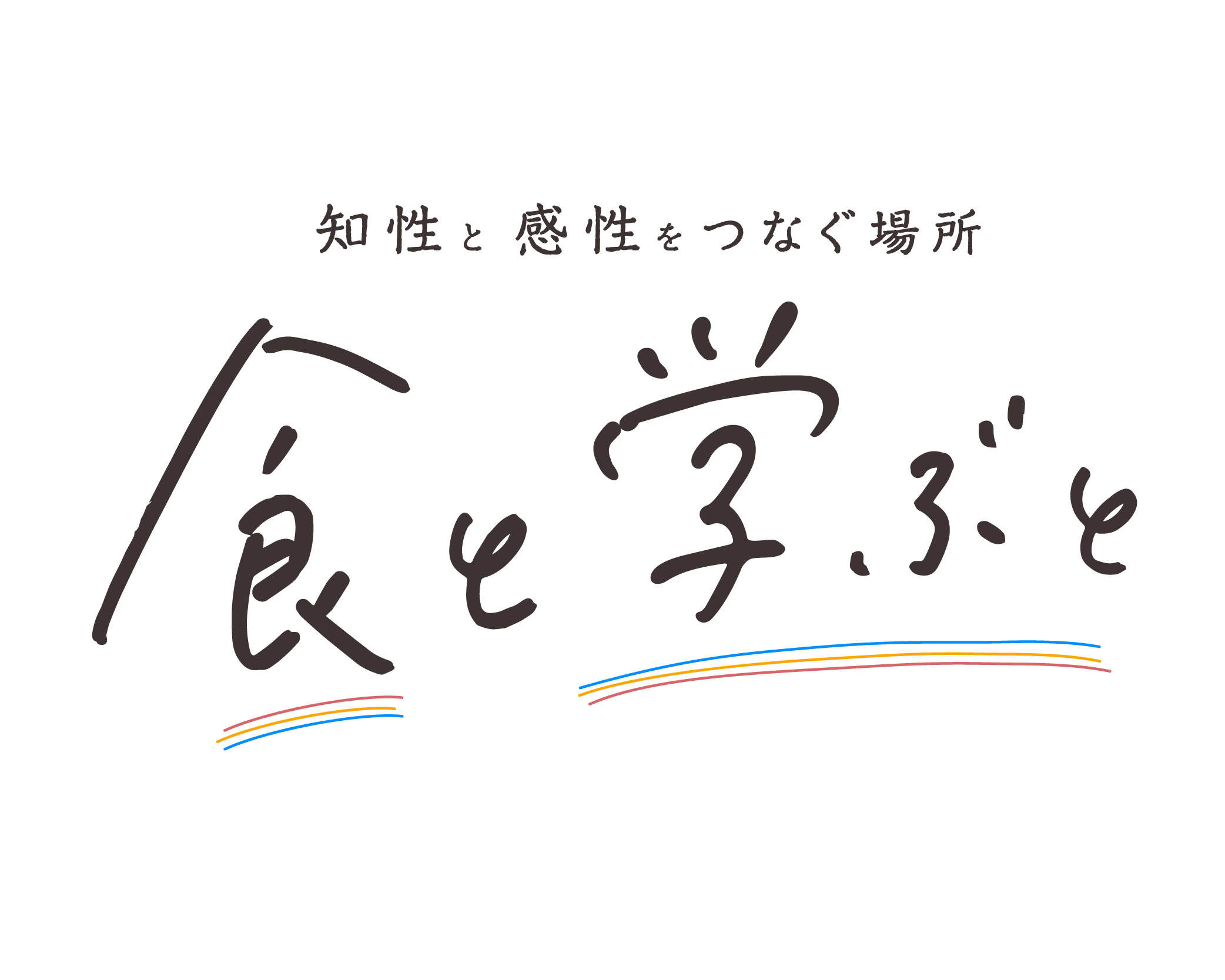中学受験で子どもが食べない…親が知っておきたい5つの工夫
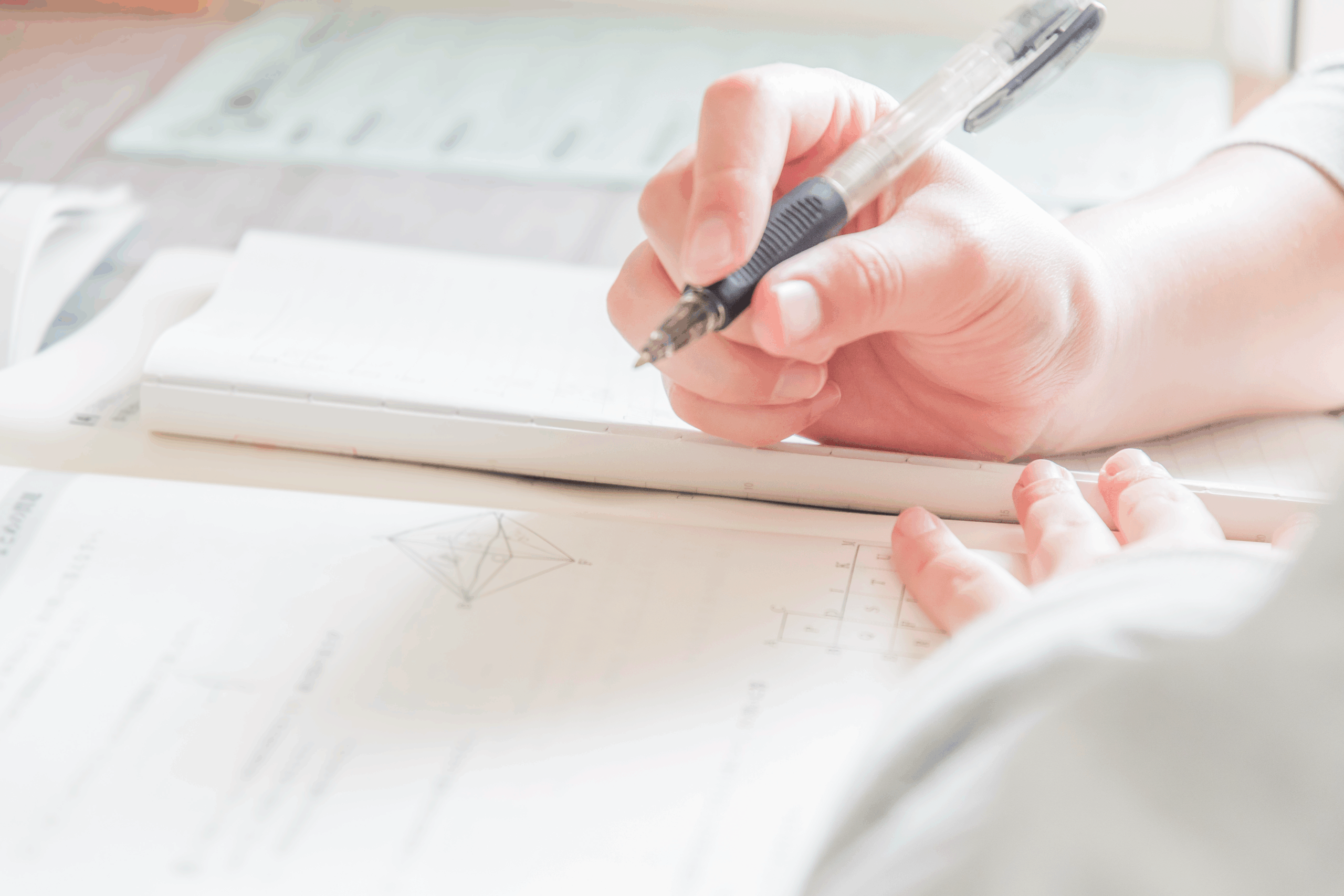
中学受験が本格化してくると、朝ごはんを食べない日が続いたり、好きだったメニューに手をつけなくなったり…。
「これって、ただの食欲不振?それとも心のSOS?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません
この時期に大切なのは、“食べさせること”ではなく、“食べられない背景に寄り添うこと”。
今回は、そんなお子さんの変化にどう向き合えばいいか、食育講師としてお話しします。
中学受験期、「食べない」はよくあること?見逃しちゃいけないサインとは
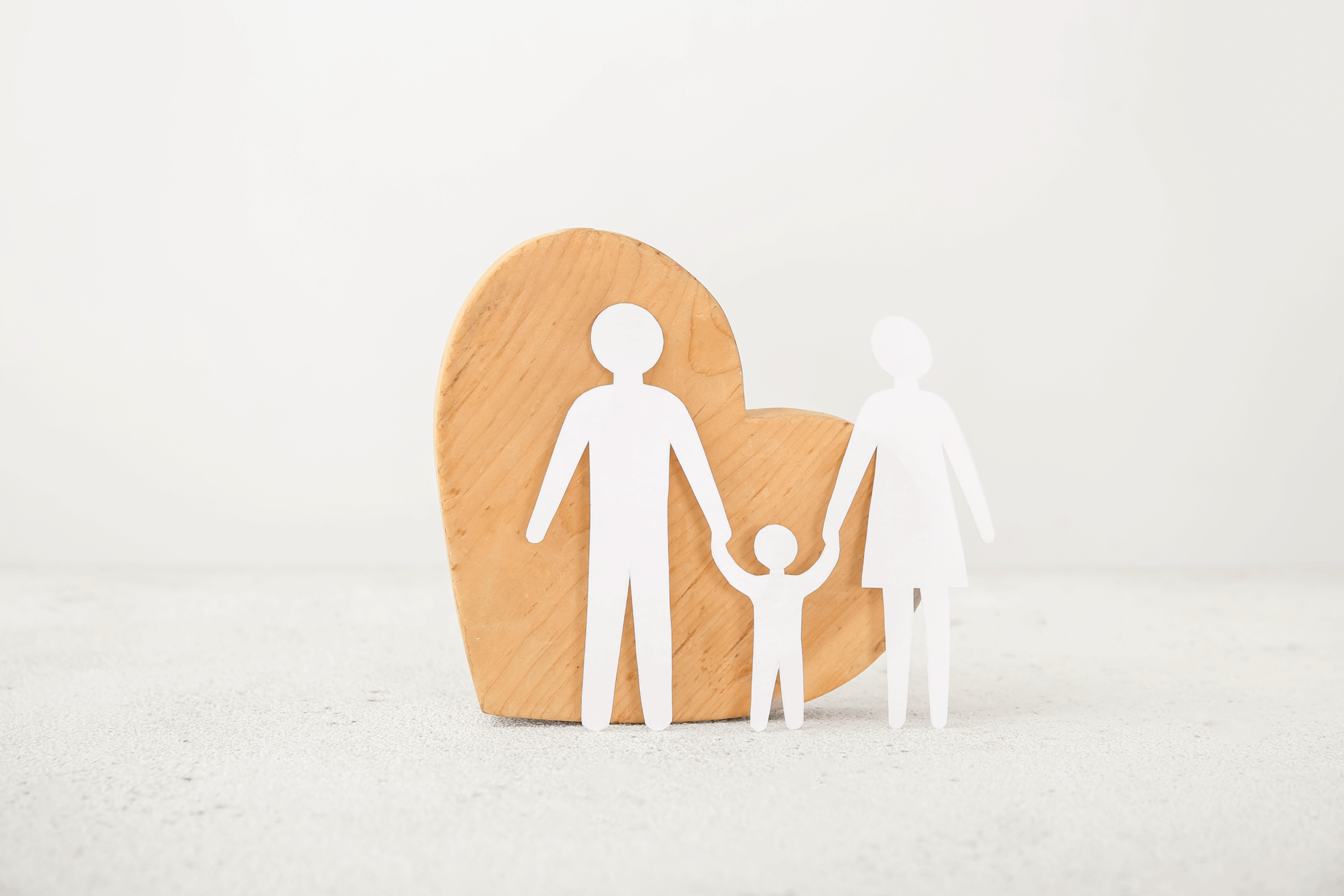
中学受験を控える時期、子どもの「朝ごはんいらない」「なんか食べたくない」という言葉が増えることがあります。
親としては「栄養が足りなくならないかな」と心配になりますが、実はこの時期、食欲に波があるのは珍しいことではありません。
ただし、その中に“気づいてあげたいサイン”が隠れていることもあるのです。
よくある“ちょっと食べない”と、注意が必要な“変化”の違い
「今日は食欲がないみたい」「昨日は夜遅かったからかな」など、日常のちょっとした要因で食べないことは、誰にでもあります。大切なのは、そうした一時的な変化なのか、少し見守りを深めたほうがいい状態なのかを見極めること。
- 前日に食べ過ぎてお腹が空いていない
- 寝不足や疲れで朝に食べる気がしない
- 勉強で頭がいっぱいで食事が後回しになる
こうしたケースでは、無理に食べさせる必要はありません。水分をとって静かに過ごしていれば、自然と回復することが多いものです。
子どもが出す「助けて」のサインに親が気づけるかどうか
ただし、以下のようなサインが複数見られる場合は、気持ちや生活リズムが乱れている可能性があります。
- 好きだったメニューにも反応が薄くなる
- 食事のときに無口になる、イライラする
- 「なんか気持ち悪い」と繰り返す
- 日中の元気がなくなり、表情が少なくなる
このような変化は、子どもなりの「今はつらいよ」「少し休みたい」という気持ちの現れかもしれません。決して大げさに不安がる必要はありませんが、「この子なりのサインかも」と心にとめておくことが、安心して次の行動に移るための土台になります。
見守り術①:食べさせるより「食べなくても大丈夫な環境」を整える

「食べさせなきゃ」と思えば思うほど、親の焦りが子どもに伝わってしまうものです。
大切なのは、“食べない”ことを責めるのではなく、「食べなくても大丈夫」と感じられる空気を整えること。子ども自身がプレッシャーから解放されると、自然と食べる意欲も戻ってくることがあります。
朝食にこだわりすぎず、子どものペースに合わせたタイミングの再設計
朝が弱いタイプの子や、目覚めてすぐに食欲がわかない子にとって、「朝ごはんの時間」はときに負担になることもあります。そんなときは、「いつ食べるか」を見直すのもひとつの方法です。
- 無理に朝一番で食べさせようとしない
- 登校直前に軽くバナナやスープだけでもOK
- 学校に持たせられる「後で食べる用」の軽食を準備する
朝の“儀式”のように構えてしまうと、うまくいかないことに親もイライラしてしまいがち。
「今日はおにぎり作っておいたから、お腹空いたときに食べてね」など、子どものタイミングを尊重することで、無理なく食べる流れができていきます。
「食べたくない」気持ちを受け止める言葉かけの例
「せっかく作ったのに」「残さないで」など、つい口をついて出てしまう言葉。
でも、食べられない子どもにとっては、そのひと言が心に重くのしかかることもあります。
おすすめなのは、“受け止める言葉”に変えていくことです。
たとえば…
- 「今はお腹が空いてないんだね。大丈夫だよ」
- 「体が休みたいって言ってるのかもしれないね」
- 「食べられるタイミングが来たら声かけてね」
そんな言葉をかけてもらうだけで、子どもは“自分の気持ちをわかってくれている”と感じ、心がふっとゆるみます。すると、「じゃあちょっとだけ食べてみようかな」と思えることもあるのです。
見守り術②:体重ではなく“表情・声・行動”に注目する

子どもがあまり食べていないと、「体重が減っていないかな」「栄養は足りているかな」と心配になりますよね。
でも、数字だけで判断しようとすると、かえって見落としがちな大切なことがあります。
実は、“食べる量”よりも“日中の元気さ”や“普段の様子”に目を向けるほうが大事なこともあるのです。
子どもの元気度を測るチェックリスト(食事以外のサイン)
食事の量が減っていても、次のような行動が見られていれば、心と体は意外と元気なサインかもしれません。
- 朝、自分で起きられる
- 登校時にスムーズに家を出られる
- 帰宅後の会話がいつも通りある
- 好きなテレビや本に笑っている
- 友だちとのやりとりを楽しんでいる
食事だけで「調子が悪い」と判断するのではなく、子どもの“全体の様子”から元気度を見てあげる視点をもつことで、過度な不安や心配を和らげることができます。
「食べない=悪い」ではない、日中元気ならOKという視点
「朝ごはんを残した…」「夕飯も半分しか食べてない…」
そんな日が続くと不安になりますが、たとえば日中を元気に過ごせていれば、それが子どもにとっての今の“ちょうどいい”状態なのかもしれません。
「ごはんを食べていない=不健康」とすぐに結びつけるのではなく、
「今日はこんなふうに過ごしていたな」と表情や声のトーンを思い出してみることも、見守りのひとつです。
無理に栄養を補おうとせず、「今のこの子に必要な量を、必要なタイミングで食べられたらOK」という柔軟なスタンスでいられると、親も子も安心して過ごせます。
見守り術③:栄養は“1週間単位”で整えてみて

「今日は全然食べてくれなかった…」と落ち込む日もあるかもしれません。でも、栄養は1日単位で完璧を目指すものではなく、“1週間”という少し長めの視点で整えていくくらいがちょうどいいのです。
「今日だけ」を気にしない。抜けても帳尻が合えばいい
朝ごはんを抜いた日があっても、そのぶん夜に少し多めに食べていたり、
別の日に野菜をたっぷり摂っていたりすれば、1週間全体でバランスが取れていればOKという考え方ができます。
毎食ごとに「食べた?足りた?」とチェックするよりも、
「今週はなんとなくいろんなものを食べられていたかな?」と、ざっくりとした感覚で振り返るくらいで十分です。
たとえば…
- 月曜は朝食べられなかったけど、夕食はおかわりしていた
- 水曜はおやつに果物とヨーグルトを食べていた
- 土日は家族で食卓を囲んで、よく食べていた
こうした全体の流れで考えることで、「栄養がちゃんと摂れてるかも」と安心できる材料が増えていきます。
朝・昼・夜ではなく「全体」でバランスをとる
毎日きっちり栄養バランスを整えるのは大変ですよね。“朝・昼・夜のうち、どこかで整えばいい”というくらいの気持ちで献立を組み立てるのはどうでしょうか。
たとえば…
- 朝はバナナ1本でもOK、昼は塾弁で主食中心、夜に野菜たっぷりの汁物
- 朝と昼が軽めなら、おやつにチーズやナッツで補給
- 夜ごはんを一緒に作ることで「作る→食べる」流れを自然に作る
“1回1回の完璧さ”よりも、“長い目で見た積み重ね”を大切にする。
その柔らかさが、子どもとの関係にも、食べることへの信頼にもつながっていくはずです。
見守り術④:「受験ストレス」が原因なら、食事以外で緩めてみよう

食欲が落ちている時期、つい「何を食べさせるか」にばかり目が向いてしまいがちですが、実はその前に、「食べる余裕がある状態かどうか」を整えることが、とても大切です。
食欲の変化は“心の疲れ”のサインかもしれない
食べる元気がないのは、栄養の問題ではなく、「気持ちがいっぱいいっぱいだから」ということもあります。
たとえば、毎日続く勉強、模試の結果、周囲との比較、親の期待…。
子どもなりにたくさんの思いや緊張を抱えていて、気持ちの余裕がなくなることで、食欲にも影響が出てくるのです。
親としては「食べなさい」ではなく、「今、がんばりすぎてないかな?」という視点で全体を見直してみるのがポイントです。
勉強スケジュールの見直し、休む勇気、親のリラックス
気持ちに余白が生まれると、自然と「お腹すいたな」「ちょっと何か食べようかな」と感じられるようになります。
だからこそ、「食事」以外の生活の中にある“ゆるめポイント”を探してみましょう。
たとえば…
- 毎日詰め込みすぎている学習計画を、少し余裕のあるものに変更する
- 模試の前日は、勉強よりも早寝と栄養補給を優先する
- 親が一緒に深呼吸したり、散歩に誘ったりして“体も心もゆるめる時間”をつくる
そして何より大事なのが、親自身がピリピリしすぎないこと。
「食べてくれない…」「受験が迫っている…」と焦る気持ちもよくわかりますが、
親の表情や言葉のトーンは、子どもに驚くほど伝わっています。
子どもが不安定なときほど、「よく寝る」「あたたかいお茶を飲む」「子どもの前で笑う」ことを意識してみましょう!親がゆるむことで、子どもも少しずつ肩の力を抜いていけるからです。
見守り術⑤:子どもに「食事の決定権」を持たせてあげる

「食べること=親に管理されるもの」と感じてしまうと、子どもにとって食事は義務やプレッシャーになってしまいます。
でも、ちょっとした関わり方で、「自分で選べる」「関われる」と思えるようになると、自然と前向きな気持ちが生まれます。
「選べる朝ごはん」「作る役割」「献立相談」などで関与を増やす
子どもが食べたくないとき、ただ一方的に「これを食べなさい」と言うよりも、小さな選択肢を用意することが効果的です。
たとえば…
- 「トーストとおにぎり、どっちにする?」と選ばせてみる
- 自分で好きな具を入れて“マイおにぎり”を作ってみる
- 週末の献立を一緒に考えてもらう
「自分で選んだ」「自分で作った」と思えるだけで、
子どもは“食べること”への抵抗感がぐっと減ります。
それは、“自分の意思で食と関われている”という安心感にもつながります。
食べる=義務ではなく、「関われること」のひとつとして捉える
「ちゃんと食べてほしい」と願う気持ちは自然なことですが、
この時期に大切なのは、“食べる”という行為を押しつけるのではなく、
“食に関わる”という体験をゆるやかに増やしていくことです。
料理の準備、買い物、盛りつけ、食卓の会話。
どれもが、子どもにとって「食と関わる」大切な入り口です。
「食べること」そのものよりも、
「一緒に考える」「一緒に楽しむ」プロセスの中で、
子ども自身の気持ちがゆるみ、自然に食が戻ってくることも多いものです。
おわりに:食べること以上に、“気持ちをゆるめる時間”が必要な時期
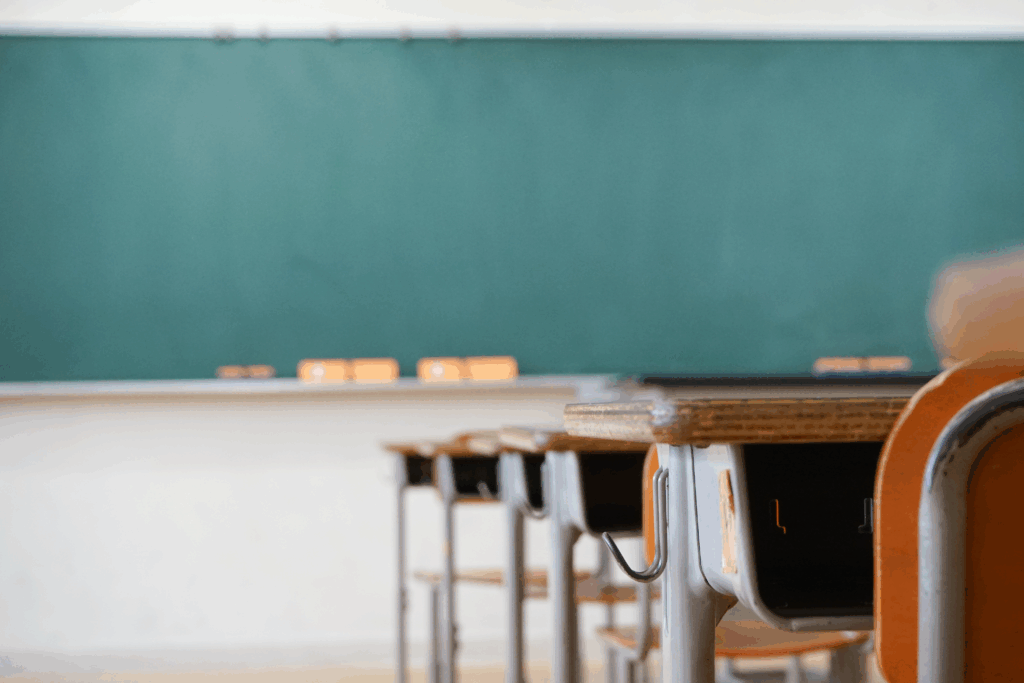
中学受験期の子どもにとって、食事は「栄養補給」だけではなく、その日の心の状態を映すものでもあります。朝食をしっかり食べられる日もあれば、まったく食べたくない日もある——そんな波があるのは、むしろ自然なことです。
親としては、「食べてほしい」「元気でいてほしい」と願うからこそ、食べない日が続くと不安になりますよね。でも大切なのは、食べさせることを急ぐより、子どもの気持ちをまるごと受けとめること。「今は無理をしないほうが、この子にとっていいのかも」と思えるようになると、親の気持ちも少しずつほぐれていきます。
朝ごはんがうまくいかない日があっても、それは“失敗した朝”ではありません。夜に「おかえり」と迎えて、一緒に食卓を囲める時間があれば、それだけで心の栄養は満たされていきます。
“完璧な食事”よりも、“笑顔で過ごせる時間”を大切に。
そんな視点をもって、親子でこの時期を一歩ずつ乗り越えていけますように。