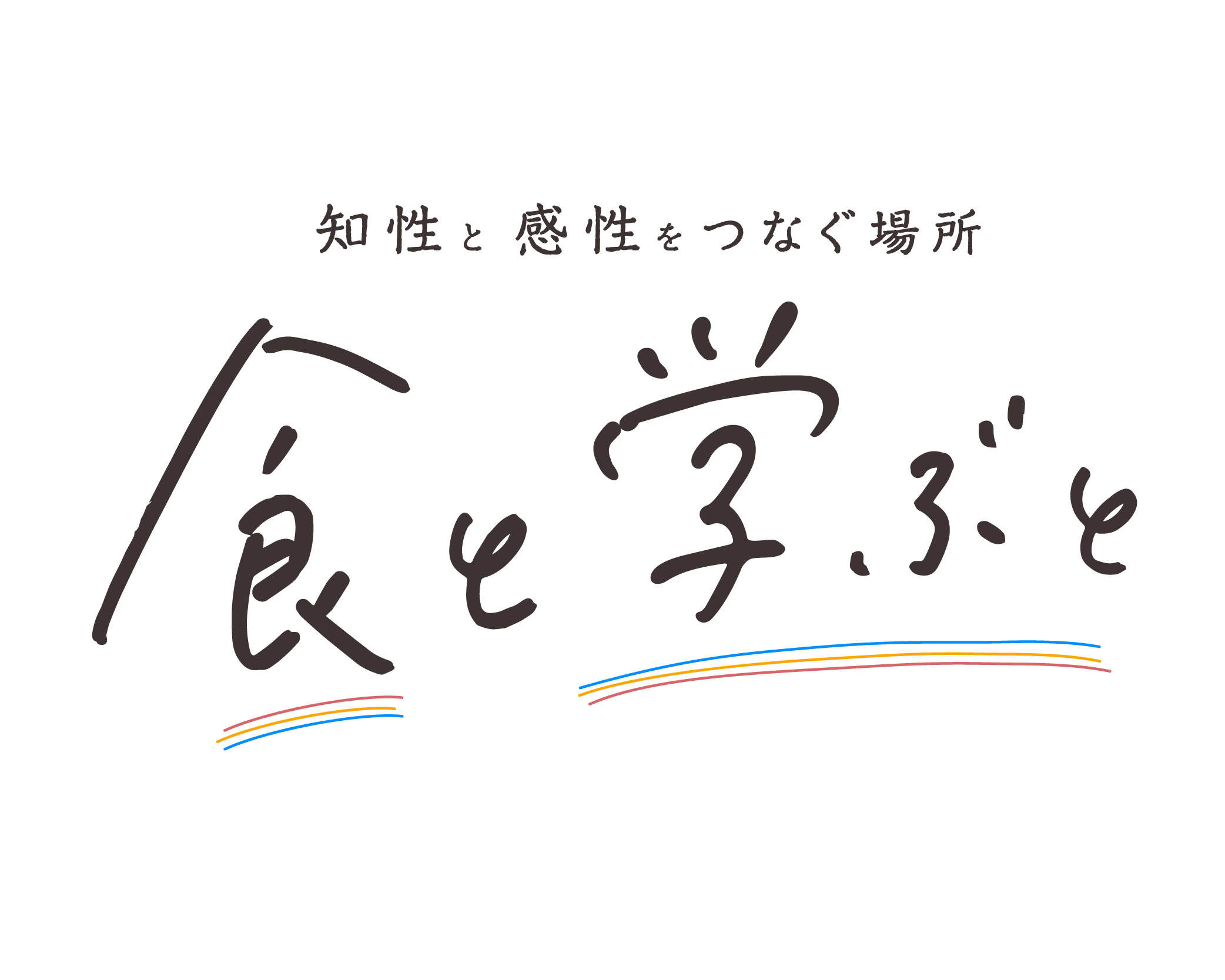中学受験期に子どもが便秘に…栄養・生活リズム・ストレスから考える3つの対処法
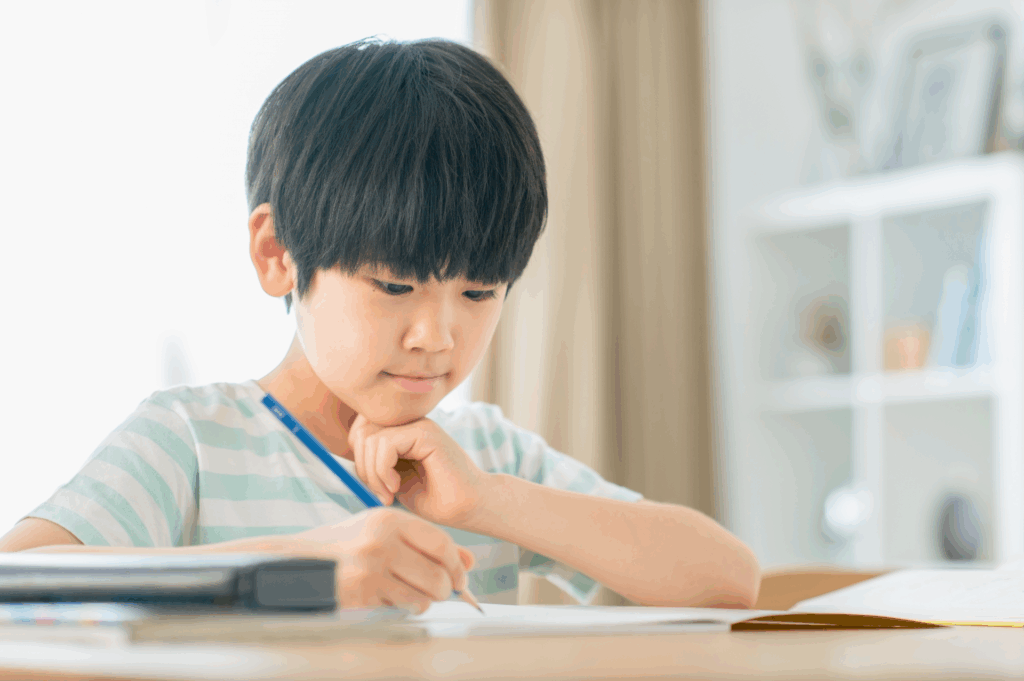
中学受験に向けて毎日頑張っている子どもたち。
でも最近「なんだかお腹が張っているみたい」「便が何日も出ていないかも…?」と、便秘のような様子に気づいたことはありませんか?
食事のバランスや生活リズムに気をつけていても、プレッシャーや緊張感が続く受験期は、心と体が微妙に影響し合って、思わぬかたちで不調が出ることがあります。
そのひとつが、“便秘”というサインです。
「食事を変えるだけでいいの?」「何か大きな原因があるのでは…」と不安になるかもしれませんが、実は少し見方を変えることで、子ども自身のペースに合った整え方が見えてくることもあります。
この記事では、受験期にありがちな“便秘気味”の子どもを、焦らず・責めず・やさしく整えていくための3つのサポート術をご紹介します。
中学受験期、便秘はよくある?子どもの心と体の変化から読み取るサイン

中学受験を控えた子どもたちは、生活のリズムが変わりやすく、心も体も緊張状態にあることが少なくありません。
そんななかで「最近、便が出ていないみたい…」という便秘のサインが見えてくることも。
これを“ただの食生活の乱れ”と片づけてしまうのではなく、「がんばりすぎていないかな?」「安心できる時間が足りていないのかも」と、心と体のつながりに目を向けてみることが大切です。
生活リズムの変化による影響も
受験勉強で早起きや夜更かしが続いたり、朝のトイレタイムが落ち着かなくなったりすると、自然な排便リズムが乱れがちです。
特に、「学校では行きたくない」とがまんをしてしまう子は、少しずつ便秘が習慣化してしまうこともあります。
子どもの緊張や不安が体に出ている場合も
体のこわばりや、呼吸の浅さ、ちょっとしたイライラ…。
これらはすべて、心の緊張が体に現れているサインです。
便秘もまた、そんな“がんばりすぎ”の一部として出てくることがあります。
まずは「今、どんな状態かな?」と見守ることから
便秘を“すぐに治さなきゃ”と捉えるよりも、子どものペースや日常の様子を観察することからはじめてみましょう。
たとえば、「最近、笑顔が少ないかも」「寝る前にため息が多いかも」など、ちょっとした変化に気づけると、心のゆとりを取り戻すきっかけになります。
中学受験期、便秘が増えるのはなぜ?

受験勉強と便秘…一見関係なさそうに思えるかもしれませんが、実はつながりはとても深いんです。
勉強時間の増加と運動不足
中学受験が本格化すると、机に向かう時間がどうしても長くなります。
放課後や休日の自由時間が減り、体を動かす機会も少なくなると、腸の動きが鈍くなってしまうことがあります。
腸は、歩いたり走ったりすることで自然に刺激されて動きがよくなります。
「ちょっとだけ散歩する」「寝る前に簡単なストレッチをする」など、日常の中に小さな運動を取り入れるだけでも違いが出てきます。
緊張・プレッシャーによるリズムの乱れ
子どもはまだ心も体も発達段階。
「模試が近い」「成績が伸び悩んでいる」など、日々のプレッシャーや緊張状態が続くと、知らず知らずのうちに腸の働きにも影響が出てきます。
また、ストレスから食欲が落ちたり、朝食を急いで食べたりするのも、排便リズムの乱れにつながります。
見逃したくない子どもの便秘サイン

便秘かどうかを見極めるのって、実はとても難しいんです。
「トイレに行っているかどうか」だけでは、本当のところはわからないこともあります。
トイレの回数だけではわからない
毎日トイレに行っているからといって、必ずしも“すっきり出せている”とは限りません。
実際、出ていても「コロコロした硬い便」だったり、「時間をかけてやっと出る」ような状態なら、便秘のサインかもしれません。
また、「トイレに行きたくない」と我慢してしまう子もいます。
塾や学校で「音が気になる」「恥ずかしい」といった理由から、排便を我慢するうちに、便秘が長引くこともあるんです。
子どもの「なんとなく不調」をキャッチする
- 「おなか痛い」とよく言う
- いつもより元気がない
- 食欲が落ちている
- イライラしやすくなった
こうした“なんとなくの不調”が、実は便秘と関係していることも。
子ども自身も「出ていないこと」に気づいていないことがあるので、親が少し気にかけてあげるだけでも、早めの対処につながります。
サポート術①:朝の“お通じルーティン”をつくる

朝の過ごし方を少し整えるだけで、腸のリズムはグッと安定してきます。
中学受験期の生活リズムの中でも、「朝のルーティン」を意識することで、自然なお通じをサポートできることがあるんです。
起床〜朝食〜トイレまでの流れを整える
まず大事なのは、「毎朝、同じ時間に起きる」こと。
起床時間が一定だと、体内時計が整い、自然と排便のリズムもできやすくなります。
そして、朝ごはんをきちんと食べることもポイント。
朝食をとることで腸が動き出し、「そろそろ出すタイミングだよ」と身体が教えてくれます。
理想は、「起きる → 食べる → トイレに行く」までを“セット”にしておくこと。
最初はうまくいかなくても、毎日の積み重ねで少しずつ体が覚えていきます。
朝食メニューの小さな工夫(例:温かい汁物、食物繊維)
朝のごはんには、腸をやさしく刺激する食材をプラスすると◎。
- 温かいお味噌汁やスープ
- やわらかめの炊きたてごはん
- きな粉ヨーグルト
- バナナやりんごなど、皮ごと食べられる果物
など、「温かい・やわらかい・食物繊維がある」ものを意識すると、朝からおなかがホッとゆるんでくれます。
無理なく取り入れられる“我が家なりのルーティン”を、子どもと一緒に見つけていくのがコツです。
サポート術②:水分補給は「量よりタイミング」

「もっと水を飲ませたほうがいいのかな?」と思うこと、ありますよね。
でも実は、水分は“たくさん飲む”よりも、“いつ飲むか”がとても大切なんです。
「飲ませる」より「自然に飲める」習慣づくり
子どもに「もっと水を飲んで」と言い続けるのは、案外ストレスになりがち。
声かけだけに頼らず、「自然と手が伸びる仕組み」をつくっておくと、ぐんとラクになります。
たとえば
- 朝起きたら、白湯や常温のお水をテーブルに置いておく
- 学習机に水筒を置いておく(こぼれにくいストロータイプもおすすめ)
- 冷たすぎない麦茶やルイボスティーなど、カフェインのない飲み物を用意する
「喉が乾いた時にすぐ飲める環境」があれば、子どもは無理なく水分をとってくれます。
冬こそ意識したい水分のとり方
気温が下がる冬は、汗をかかないぶん「水分不足に気づきにくい」季節。
それが腸の動きを鈍らせてしまう原因になることもあります。
寒い季節には:
- スープや味噌汁など“食べる水分”を活用
- おやつにみかんやゼリーなど水分の多いものを取り入れる
- 外出から帰ったら一口飲むなど、“タイミングルール”を決めておく
こうした“こまめな補給”が、からだ全体のめぐりを整えてくれます。
サポート術③:緊張をほぐす「おなかにやさしい夜時間」

中学受験期の夜は、子どもにとっても“がんばる時間”。
でも、寝る直前まで頭がフル回転していると、心も体もゆるまらず、腸も動きづらくなります。
就寝前のリラックスと腸の関係
私たちの腸は、自律神経のバランスに大きく影響を受けます。
とくに夜の時間に“緊張モード”が続くと、腸の働きもストップ気味に。
だからこそ、寝る前の“ほっとする時間”がとても大切です。
おすすめは
- ほんの5分、ストレッチや足湯などのリラックスタイム
- 照明を落として、静かな音楽を流す
- ベッドで「今日よくがんばったね」と一言、気持ちを緩めてあげる
おなかだけでなく、心の緊張もふっとほどけることで、自然とめぐりが良くなっていきます。
夜ごはんと“寝るまでの時間”を見直す
寝る直前にたっぷり食べてしまうと、体は消化にエネルギーを使ってしまい、リラックスどころではなくなってしまいます。
夜ごはんのポイントは
- 消化のよいもの(やわらかく煮た野菜、汁物など)を中心に
- 食事から寝るまでに1〜2時間あけるようにする
- おなかを冷やさないよう、温かい飲み物でしめるのも◎
「寝る前までがんばる子どもを、やさしく包むような夜の習慣」。
そんなふうに捉えてみると、心も体も少しずつ整っていきます。
出すことは“整えること。親子で無理なく向き合っていこう

便秘は「出ないこと」だけが問題ではありません。
心と体のバランスが少しだけ乱れているサインかもしれない――そう思って、やさしく見守る視点を持てたら、子どももきっと安心します。
中学受験は、子どもにとっても親にとっても、大きなチャレンジの時期。
学びを支えるには、まず“整った体”がベースになります。
朝のリズム、水分のとり方、夜のリラックス。
どれも特別なことではないけれど、毎日の中にちょっとずつ取り入れていくことで、子どもは自分の体とのつき合い方を自然と覚えていきます。
もし、便秘が長引いたり、子ども自身がつらそうにしている場合には、遠慮せず小児科や薬剤師に相談してみてください。
「気になるな」と思った時点で行動しておくと、親子の安心にもつながります。焦らず、ゆっくり、親子で一緒に整えていきましょう。