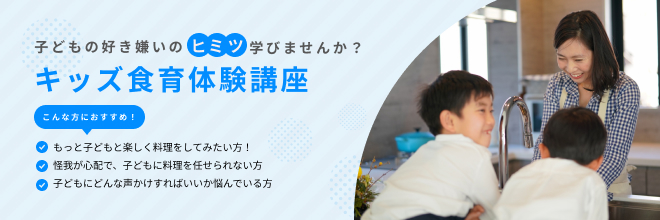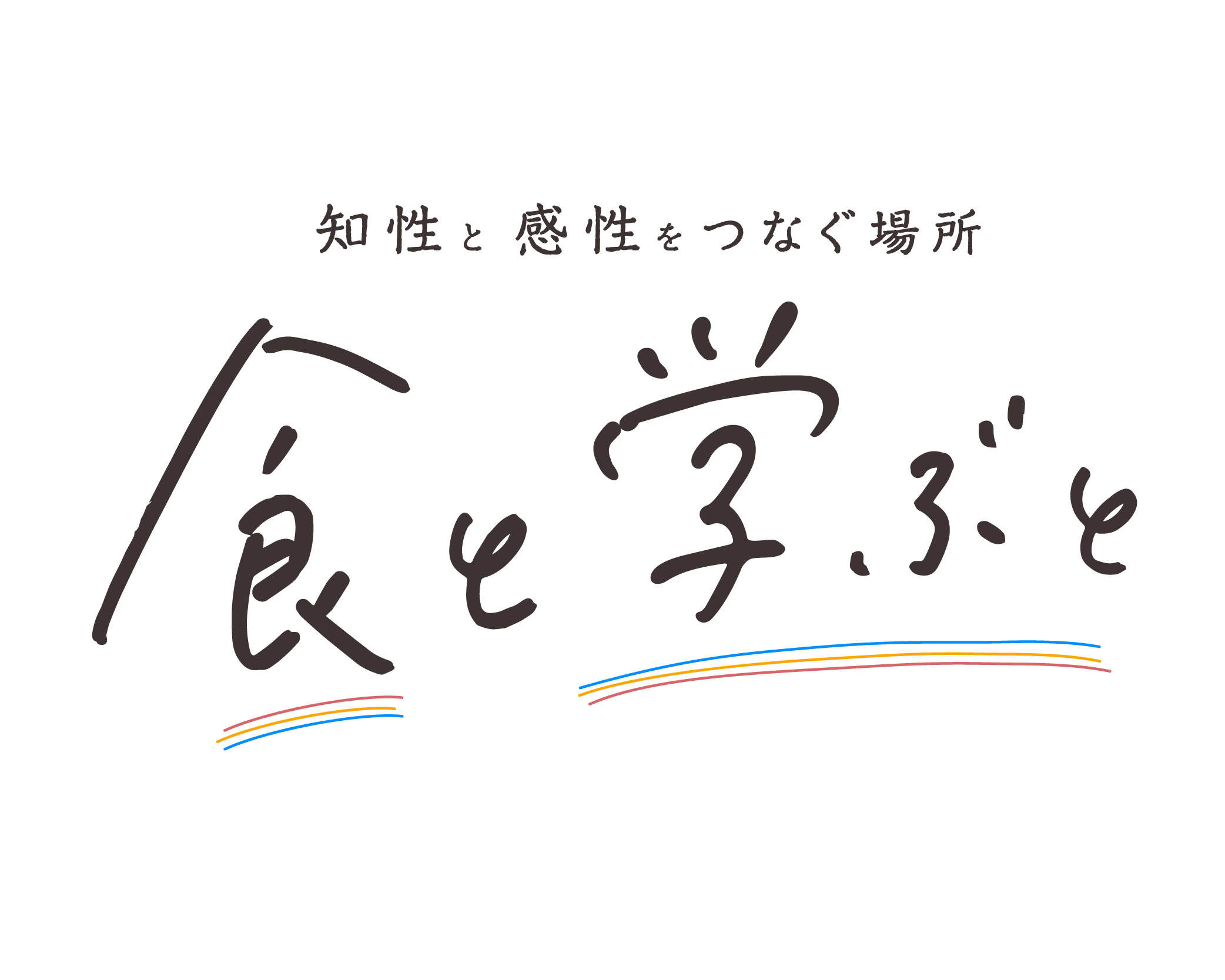子どもと楽しむ梅しごと|梅シロップ作りで季節の体験を

「梅しごとって難しそう…」「子どもと一緒にできるの?」と感じている方にこそ、ぜひ体験してほしいのが梅シロップ作りです。
実はこの梅しごと、親子で楽しめる季節の手仕事としてぴったり。香りや手触り、味の変化など五感を使った体験を通して、自然や食への興味が育まれます。
この記事では、小さな子どもでも安心して取り組める「梅シロップ作り」のやり方を中心に、梅しごとを親子で楽しむコツやアレンジアイデアをご紹介します。
梅しごとってなに?子どもと楽しむ季節の手仕事

梅しごとは、初夏の訪れを感じながら、梅を使って梅干しや梅酒、梅シロップなどを仕込む日本の季節行事です。
とくに「梅シロップ」は、小さな子どもでも安心して関われる、親子の梅しごとデビューにぴったりの手作り体験です。
昔ながらの知恵が詰まった梅しごとは、日々の暮らしに季節感を取り戻す貴重な時間でもあります。「今年も梅の季節が来たね」と親子で季節を感じながら取り組むことが、食育や感性の土台にもつながっていきます。
「梅しごと」ってどんなもの?
梅しごととは、毎年5〜6月ごろに旬を迎える青梅や完熟梅を使って、保存食を仕込む手仕事のこと。
梅干し、梅シロップ、梅酒などが定番ですが、そのどれもが保存がきいて、日々の暮らしを豊かにしてくれる存在です。
中でも「梅シロップ」はアルコールを使わないため、子どもと一緒に作るのにぴったり。時間の経過とともに、梅のエキスが氷砂糖に溶けてシロップになっていく様子は、まるで理科の実験のようなワクワク感があります。
「梅しごと」を親子で楽しめる理由
子どもにとっての梅しごとは、まさに“全身で感じる体験”。
・手で梅を洗うときのひんやりとした感触
・ふわっと立ちのぼる青梅の香り
・氷砂糖のカリカリとした音
…そんな小さな発見の連続が、子どもの五感を刺激します。
また、「仕込んだあとは毎日瓶をゆらすだけ」「完成まで2週間ほど待つ」という工程も、せかせかした日常とはちがう“待つ楽しみ”を親子で味わえるポイントです。
梅しごとの時期とタイミング
梅しごとに使う青梅は、地域差はありますが5月下旬〜6月中旬にかけて店頭に並びます。鮮度が命なので、見つけたらなるべくその日に作業を始めるのが理想です。
梅の実を通じて、「今だけの季節」があることを子どもに伝えるきっかけにもなります。「来年もまた一緒にやろうね」と、親子の季節の習慣になっていくことも多いですよ。
梅シロップ作りに必要な材料と道具

梅しごとを始めるときに、まずそろえておきたいのが材料と道具です。基本の道具さえあれば、あとはスーパーで手に入るもので気軽に始められます。
準備する材料(青梅1kg分)
- 青梅 1kg
- 氷砂糖 1kg
- 消毒用アルコール(または焼酎)少々
氷砂糖を使うことで、ゆっくりとシロップが出てきて、風味もやさしく仕上がります。
甜菜糖やきび糖でも代用可能ですが、濁りや発酵しやすさが変わってくるため、はじめての梅しごとでは氷砂糖がおすすめです。
使用する道具
- 保存瓶(4Lサイズの広口ガラス瓶)
- ボウル
- ざる
- 竹串または爪楊枝(ヘタ取り用)
- 清潔な布巾やペーパータオル
保存瓶は煮沸消毒できるガラス製が最適。ふたがしっかり閉まるものを選びましょう。最近は、100円ショップやホームセンターでも手頃な価格で手に入ります。
瓶の消毒はしっかりと
梅シロップ作りでいちばん大切なのが「清潔さ」。
梅のエキスが出るまでのあいだに雑菌が入ってしまうと、発酵やカビの原因になります。
瓶は熱湯で煮沸消毒するか、アルコールを全体にスプレーして布巾で拭き取りましょう。梅の実や道具も水分をしっかり拭き取ってから使います。
親子で作ってみよう!梅シロップの仕込み方

梅シロップ作りは、シンプルな手順で完成までの変化を楽しめる季節の手仕事です。
時間がかかる分、親子で「待つ楽しさ」や「観察する面白さ」も味わえます。
梅シロップの下準備
- 梅を洗う
ボウルにたっぷりの水をはり、青梅をやさしく洗います。ゴシゴシこすらず、傷つけないように注意。 - 水気をしっかり拭き取る
ざるにあげたら、布巾やキッチンペーパーで丁寧に水気を拭き取ります。ここをしっかりするとカビのリスクが減ります。 - ヘタを取る
竹串や爪楊枝で、梅のヘタ(黒いポチっとした部分)を取り除きます。子どもにも任せやすい工程です。 - 梅を冷凍する(お好みで)
すぐに漬けてもよいですが、一度冷凍すると繊維が壊れてエキスが出やすくなります。
瓶に詰める
- 瓶を消毒して乾かす
煮沸またはアルコール消毒を行い、しっかり乾燥させておきます。 - 梅と氷砂糖を交互に入れる
梅→氷砂糖→梅→氷砂糖…と交互に重ねるように入れます。これも子どもが楽しめるポイント。 - ふたを閉めて、涼しい場所に置く
日光の当たらない、風通しのよい室内で保管します。
できあがりまでの観察を楽しもう
1日1回、瓶を軽く揺すって中身をなじませます。
だんだんと梅のエキスが出てきて、透明なシロップが下にたまっていく様子を毎日観察できます。
10日〜2週間ほどで飲みごろに。
味見をしながら「あとどのくらいかな?」と話すのも親子の楽しみのひとつです。
五感を使う梅しごとが“学び”につながる理由

梅しごとは、ただの保存食作りではありません。におい・色・手ざわり・音・味――すべての感覚を使う体験は、子どもたちにとって特別な学びの時間になります。
手に触れる梅の感触、鼻に届く爽やかな香り、氷砂糖がカランと響く音——
梅しごとは、まさに五感をフルに使う体験です。
「この匂い、初夏って感じがするね」
「梅の手触りって気持ちいい」
そんなひと言が出てきたら、それはもう立派な“季節の記憶”。
日本の四季を感じる力が、自然と育ちます。
手ざわりを感じる
梅の実を手に取ったときの、硬さやつるんとした感触。水洗いやヘタ取りの工程で、「冷たい!」「ぬるぬるする!」といった感覚を楽しむことができます。
感触を言葉にする練習にもなり、語彙力や表現力の育成にもつながります。
香りを感じる
ヘタを取ったときや、シロップが少しずつ発酵して香りが立ってくるとき――梅特有の爽やかなにおいに気づく子どもも多いはずです。梅から水分が出てくる理由、氷砂糖が溶ける過程、発酵すると泡が出てくる変化など、子どもが疑問をもつ瞬間があります。
そんなときは、「なんでだと思う?」「調べてみようか」と問いかけて、学びの入り口を開いてあげましょう。
「いい匂い」「ちょっと酸っぱいね」といった、においに対する反応から、感性が育ちます。
色の変化を観察する
氷砂糖が溶けていく様子、梅からエキスが出てくる過程、透明な液体が徐々に黄金色に変わっていく――
こうした変化をじっくり観察することで、自然の不思議さや、時間の流れを実感することができます。
音や味も感じてみる
瓶に氷砂糖を入れるときの「カラン」という音。できあがったシロップの甘酸っぱさ。
五感すべてをフル活用する梅しごとは、まさに“生きた学び”を親子で体験できる絶好のチャンスです。
完成までの“見守り期間”も一緒に楽しむ
梅シロップは、漬けてから完成までに2〜3週間かかります。その間、毎日観察して「今日はどんなふうになってる?」と一緒に見てみることが、親子のコミュニケーションにもつながります。
待つ時間を楽しむ経験は、子どもにとって貴重な心の育ちの時間にもなります。
完成した梅シロップを使ったアレンジ例

完成後の楽しみも、梅しごとの魅力のひとつ。
梅シロップはそのまま飲むだけでなく、さまざまなアレンジが可能です。
- 炭酸水で割ってさっぱり梅ソーダ
- かき氷にかけて季節のおやつ
- ヨーグルトやゼリーにかけてデザート風に
「今度はこうしてみようか?」と話しながら、一緒に考える時間も学びの一部。
作ったあとの楽しみまで含めて、長く記憶に残る体験になります。
梅シロップ作りをもっと楽しく!親子時間の工夫

ただ作るだけで終わらせないのが、親子で楽しむ梅しごとの醍醐味。
ちょっとした工夫を加えるだけで、自由研究やクリエイティブな遊びにもつながります。
日記や記録をつけて自由研究にも
梅シロップが完成するまでの様子を、日記や観察ノートにまとめてみましょう。
- 毎日の変化(色・におい・氷砂糖の溶け具合など)を記録
- 写真を撮って貼りつけてもOK
- 「今日の気づき」「味の想像」など自由な書き方でOK
これだけでも、立派な夏休みの自由研究に!
文章が苦手な子でも「絵で描く」「親子で対話しながらメモする」といった工夫で楽しく取り組めます。
完成したらラベルづくりで名前をつけよう
完成した梅シロップに、自分だけの名前をつけてラベルを貼ってみましょう。
- 「〇〇ちゃん特製うめしろっぷ」
- 「〇月〇日仕込み・できたて梅ジュース」など
ラベルづくりを通じて、「自分で作った」達成感が深まります。
ラベルを並べて保存すれば、毎年の味比べも楽しめます。
味比べや色比べで科学的視点も育てよう
同じ梅でも、熟し加減や氷砂糖の量によって仕上がりが違ってきます。
- 「今年のはちょっと黄色っぽいね」
- 「この瓶のほうが甘い気がする」など
五感を使って感じた違いに名前をつけたり、考えたりすることで、
子どもの中に“科学の目”が育ちます。
「なんでこうなったんだろう?」の疑問が、次の探究心につながっていきます。
まとめ:梅しごとは、親子で味わう季節の宝物
忙しい毎日のなかでも、季節の節目を感じられる「梅しごと」は、親子で取り組むのにぴったりの手仕事です。
ひとつひとつの工程に、子どもが感じたり、考えたりできる余白がたっぷり詰まっていて、大人にとってもゆったりとした時間になります。
梅の香りや手触り、変化していく色や味。数日かけて変化を見守るこの体験は、「待つ時間」から学ぶことや、家族で過ごす穏やかな時間の尊さを伝えてくれます。
完成した梅シロップが並ぶキッチンは、きっとその家庭らしい夏の風景になるはず。親子で「うちの味」を育てていく梅しごと、ぜひ一度体験してみてください。