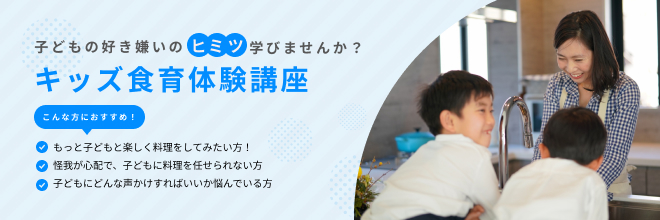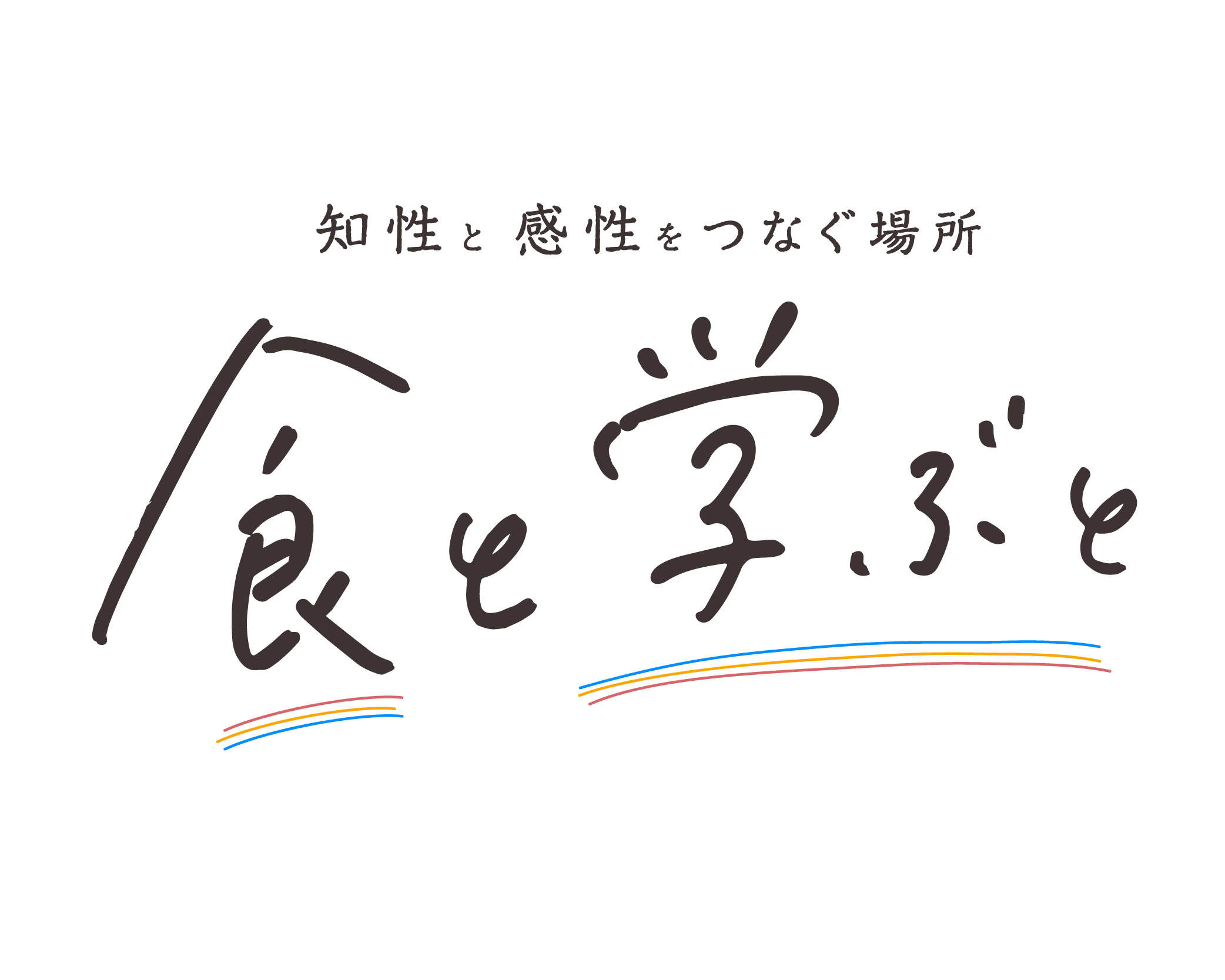お月見団子を子どもと手作り!簡単レシピで行事を楽しもう

秋の夜空に浮かぶまんまるお月さまを眺めながら、親子で一緒に過ごす“お月見”。
その時間をもっと特別にするのが、「手作りのお月見団子」です。
市販のものを買うのも手軽ですが、子どもと一緒に作ることで、季節の行事をぐっと身近に感じられます。
コネて、丸めて、茹でて──もちもちの団子ができあがるまでの工程は、まるで小さな科学実験のよう。
今回は、3歳ごろから楽しめる簡単なお月見団子レシピと、お手伝いポイント、行事にまつわる小ネタもご紹介。
「どうしてお団子を飾るの?」「何個並べるのが正解?」など、子どもの“なんで?”に答えながら、秋の思い出づくりをしてみませんか?
お月見団子ってどんなもの?由来や意味を親子で知ろう

お月見団子は、十五夜や中秋の名月に、収穫への感謝と豊作祈願を込めてお供えする伝統的な和菓子です。
白くて丸い団子は、まんまるのお月さまを表しているとされ、神様にお供えしたあとで家族でいただくことで、福を分け合う意味があるとされています
地域によっては、里芋の形をした団子や、串に刺した形のものも見られますが、基本は“白くて丸い団子を十五個”飾るのが古くからのならわしです。
子どもに伝えたい、お月見の豆知識
・なぜ「十五夜」と呼ぶの?
→旧暦の8月15日が、一年で最も美しい満月とされていたためです。
・なぜ団子を飾るの?
→秋の収穫に感謝する気持ちを、月の神様に伝えるためとされています。
・どうしてススキを一緒に飾るの?
→稲穂の代わりに飾られるようになったもので、魔除けの意味もあるそうです。
お団子作りの前に、こうした話を子どもと一緒にするだけでも、お月見が特別な行事として心に残ります。
「お団子って、ただ食べるだけじゃないんだね!」と、季節の行事に込められた意味を自然と感じられる時間になります。
子どもと一緒に!手作りお月見団子レシピ

お団子づくりは、小さな子どもでも手を動かしながら楽しめる食育体験です。
ここでは、お月見にぴったりな、もちもちでやさしい甘さのお団子レシピをご紹介します。
手軽にできて、しかも見た目もかわいく仕上がるので、季節の行事にぴったりです
材料と準備する道具
【材料(約15個分)】
- 白玉粉 100g
- 絹ごし豆腐 100g
- 紫いもパウダー 小さじ1/2(または加熱してつぶした紫いも)
- かぼちゃパウダー 小さじ1/2(または加熱してつぶしたかぼちゃ)
- 水 適量(必要に応じて)
- 黒みつ、きな粉、あんこなど(お好みで)
【道具】
- ボウル
- 計量スプーン
- 鍋
- ざる
- トングまたはおたま
もちもち&優しい甘さの団子の作り方
- 白玉粉に絹ごし豆腐を加えて混ぜ、耳たぶ程度のやわらかさになるまでよくこねる
- 生地を3等分し、それぞれに紫いもパウダー・かぼちゃパウダーを加えて着色(1つはそのまま白)
- それぞれの生地を直径2cmほどの団子状に丸める
- 沸騰したお湯に入れてゆでる。団子が浮かんできたら1〜2分ほど茹で、冷水にとる
- 水気を切って器に盛り、お好みで黒みつやきな粉をかけて完成!
カラフルにする野菜パウダー活用アイデア
- 紫いも:ほんのり甘く、淡い紫色に
- かぼちゃ:やさしい黄色で彩りアップ
- ほうれん草パウダー:緑色も加えれば、さらににぎやかに
- パウダーがなければ、加熱した野菜を裏ごしして加えてもOK
色とりどりのお団子は、子どもも夢中になること間違いなしです。色の違いを比べながら「どれが好き?」と話すのも楽しい時間になります。
年齢別・子どもに任せたいお手伝いポイント

お月見団子づくりは、年齢に合わせた関わり方で、子どものやる気や達成感を引き出せる絶好のチャンスです。ここでは、年齢ごとにおすすめのお手伝い内容をご紹介します。
3歳〜:こねる・丸める
手指の発達を促すこの時期には、感触を楽しむ作業がおすすめです。
- 白玉粉と豆腐をこねる感触を味わう
- 手のひらで団子をくるくると丸める
- 「まんまるだね!」と声をかけながら形を整える
丸めたお団子が自分の手から生まれる体験は、子どもの自己肯定感につながります。
5歳〜:計量・色付け
少しずつ数字や順序が理解できるようになる年齢です。
- 材料を計ってボウルに入れる
- 紫いもパウダーやかぼちゃパウダーを混ぜて色をつける
- 「これくらいかな?」と考える力を育てる
混ぜた色が変化する様子は、ちょっとした実験気分。食育と科学の要素も取り入れられます。
小学生〜:茹で作業の見守りサポートも
火や熱を扱う作業にも、挑戦意欲が高まる時期です。
- 団子を鍋に入れるときのサポート(大人と一緒に)
- 浮かんできたらトングで取り出す作業
- ゆであがりの違いを観察する
火の扱いには大人の見守りが必要ですが、「ちょっと大人の仕事」を任せることで、自信と達成感を得られます。
お団子をもっと楽しく!アレンジや飾りつけアイデア

せっかくの手作りお月見団子、見た目も華やかに仕上げて、子どもが思わず笑顔になるような工夫をしてみませんか?見た目の楽しさは、食べる意欲にもつながります。
色とりどりの野菜パウダーでカラフルに
白、ピンク、黄色、緑など、色とりどりのお団子はそれだけでごちそうに見えます。着色には、自然な素材を使うと安心です。
- 紫いもパウダーで淡い紫
- かぼちゃパウダーで明るい黄色
- ほうれん草パウダーでやさしい緑
- にんじんパウダーでオレンジ風
それぞれ少量のお湯でといてから生地に混ぜると、鮮やかな色合いが楽しめます。
トッピングで季節感アップ
- 粉砂糖で“月の光”を表現
- あんこやきなこ、黒みつで和風スイーツ風に
- 星型のチーズや野菜で、七夕風のアレンジにも
秋の風物詩である“すすき”を添えてみるのも、お月見らしさを演出するアイデアです。
団子をもっと楽しく!盛り付けと行事のアレンジ

盛りつけや飾りつけを工夫するだけで、子どもたちの興味もぐんとアップしますよ!
せっかくのお月見団子づくり、ただ作って食べるだけでなく、行事の意味や文化に触れる工夫を加えることで、もっと豊かな体験になるので、親子で楽しむのがおすすめです。
ススキやうさぎ型の飾りで“らしさ”を演出
お月見といえば、やっぱり“ススキ”と“うさぎ”。テーブルの一角にススキを飾ったり、お団子のそばにうさぎの形をした飾り(折り紙やピック)を添えたりすると、一気に“お月見らしさ”が引き立ちます。
手作りの折り紙うさぎを飾るのもおすすめ。子どもと一緒に作れば、料理+工作の楽しい時間にもなります。
お皿や団子の並べ方も“学び”に
お団子を三段に重ねるのは、古くからの日本の風習です。上から順に3個・2個・1個とピラミッド状に積み上げることで、美しさと意味を感じられます。
また、お皿に丸く円を描くように並べることで、「月の満ち欠け」や「形のバランス」について話しながら学びの時間にもつながります。
盛りつけひとつで、“見る力”や“感じる力”を刺激する機会になります。
地域や文化による違いを話してみよう
実は、お月見団子の形や並べ方は、地域によってさまざま。例えば関西では丸ではなく細長い団子を供える風習もあります。
「どうして形が違うんだろう?」「どこの地域の文化だろう?」といった問いかけを通して、文化の多様性や日本の伝統について親子で話すきっかけにもなります。
手作りお月見団子で育まれる食育と親子の時間

お月見団子を一緒に作ることは、単なる「食事の準備」にとどまりません。季節を感じ、伝統に触れ、会話を楽しみながら、子どもにとって豊かな“食育体験”になります。
季節の変化を五感で感じる
秋の夜風、まんまるお月さま、もちもちのお団子、やさしい甘み——お月見団子づくりは、視覚・触覚・味覚・嗅覚・聴覚を総動員して楽しめる、五感の体験そのものです。
団子を丸める感触や、茹でたときの香りなど、子どもたちにとってはすべてが新鮮な発見。「季節を感じるってこういうことなんだ」と、言葉ではなく体験で伝えることができます。
家庭でできる“行事食体験”の価値
昔ながらの年中行事は、忙しい現代ではつい忘れがち。でも、手作りのお月見団子を通して“行事食”を体験することで、子どもにとって「家族で季節を祝う」感覚が自然と身につきます。
お店で買うのではなく、家庭で一緒に作るというプロセスには、“食”への関心と、家族文化を築く力がぎゅっと詰まっています。
一緒に作ることで生まれる会話と自信
「うまく丸められたね」「きれいに並べられたね」そんなひと言が、子どもの自己肯定感を育てます。
小さな手でこねた団子がかたちになり、食卓に並ぶという経験は、大きな自信にもなります。お団子作りを通して自然と会話が生まれ、親子の心の距離もぐっと近づきます。
まとめ:お月見団子を子どもと作る体験が、心に残る秋の思い出に
お月見団子を子どもと一緒に手作りする時間は、季節の行事を五感で味わう特別なひととき。まんまるの団子に込められた想いや日本の伝統を、楽しく・おいしく伝えることができます。
粉をこねる手のぬくもり、茹で上がったお団子の香り、家族の笑顔がそろう食卓——そのすべてが、子どもの記憶に温かく刻まれていきます。
「また作りたいね」「次はうさぎの飾りも作ってみたいな」そんな会話が自然と生まれる体験こそ、親子にとってかけがえのない秋の思い出となるはずです。
忙しい毎日でも、ほんの少しの時間をお月見団子作りにあててみてください。親子で一緒に作って味わうことが、きっと“季節を楽しむ心”を育ててくれます。