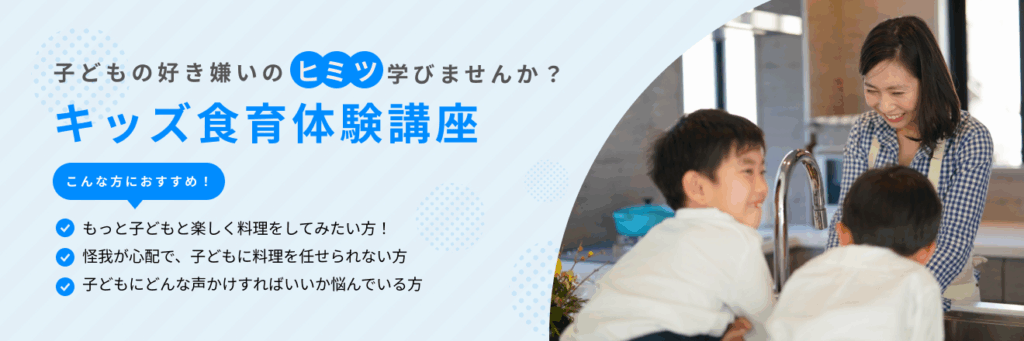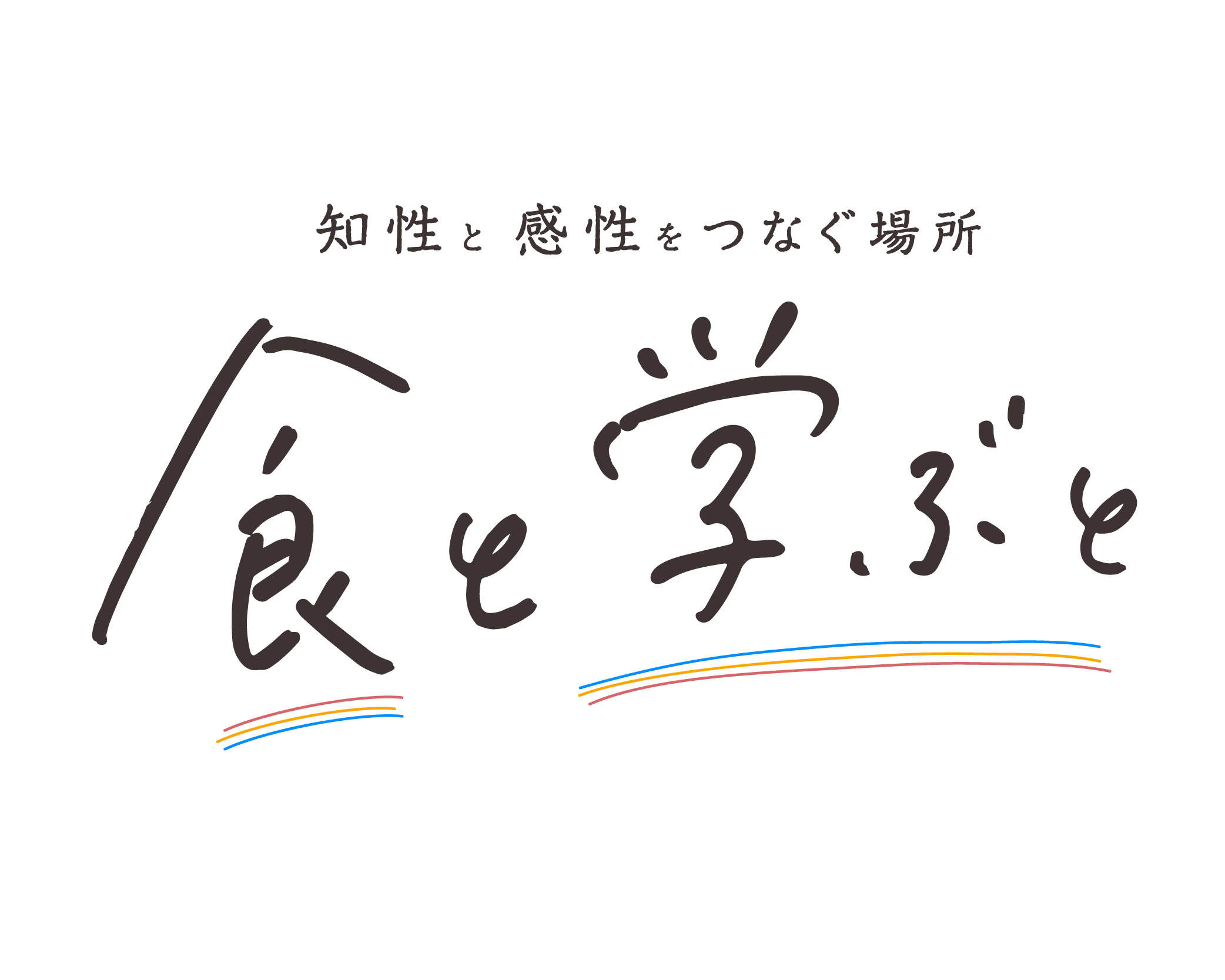2歳の食事にイライラする前に。「自分で食べたい!」「これイヤ!」成長段階と好き嫌いのしくみ

2歳の自分でやりたい!とイヤイヤ期の食事。食べない・好き嫌いをどう乗り越える?
2歳は、「自分でやりたい!」の気持ちが急に高まってくる時期です。自分で着たい!履きたい!窓を開けたい!エレベーターのボタンを押したい!など、喜ばしい反面、時間や手間もかかる…。働くママにとっては「早くしてほしい」とイライラしてしまう場面も多いのではないでしょうか。私自身、0歳を抱っこしながらの2歳の息子の子育てに、何度ため息をついたことかわかりません。食事のシーンでも、自分で食べたい。スプーンを持ちたい!といった気持ちも芽生えますし、さらにこの時期は、「好き嫌い」が目立ってくることもあります。
「昨日は食べたのに今日は全然食べない」「同じものばかり欲しがる」。
復職後の慌ただしい毎日の中で、「きちんと食べてくれない」ことが大きな不安やストレスになりがちです。でも、この不安やストレスが少しでも解消されたら…。毎日の食事の時間が楽しい時間に変わりそうですよね。
今回は、子どもの成長段階と好き嫌いの仕組みを理解して、少し心を軽くできるヒントをお伝えします。
「自分でやりたい!」は心の成長のサイン
2歳前後の子どもは、自分で靴を履きたい、クレヨンをもちたいなど、食事に限らず「自分でやりたい」という気持ちが大きく膨らむ時期です。食事の場面では、
- スプーンを持ちたい
- 手づかみで食べたい
- ママやパパと同じものが食べたい
これらは、心の成長や自立に向かうサインです。
「自分でやりたい」という意欲を受け止めてもらう経験は、安心感や自己肯定感を育み、言葉かけや、スキンシップを通して、親子の愛着形成が成されていきます。

「食べたい=きちんと食べる」ではない
ここで気をつけたいことが、大人の「食べたい」と、子どもの「食べたい」が違う意味を持つ可能性があるということです。子どもの「食べたい」はきちんと食べるではないのです。スプーンを持ってみたい。という気持ちは、正しい持ち方をしたいわけでも、こぼさずすくいたいということでもなく、「持ってみたい」という気持ちです。ですので、2歳という時期は、食べ方や、食べた量よりも、「やってみたこと」への共感や、出来たことへの誉め言葉が、自己肯定感を育み、のちの食事習慣の土台になっていきます。
2歳ごろから現れる好き嫌いの正体
2歳でよく見られる「好き嫌い」には、いくつかの理由があります。
- 苦みや酸味などを本能的に避ける(味覚の敏感さ)
- 初めて見る食べ物への警戒心
- 親の反応や食卓の雰囲気に左右される
つまり好き嫌いは多くの場合、後天的につくられるものなのです。
ですので、2歳ごろから好き嫌いが出てきたら、「あぁ、この子は順調に成長しているんだわ」と喜んでいいことなのです。
環境が子どもの食欲を変える
食事をする環境や状況も子どもの好き嫌いには大きな影響を与える可能性があります。 「時間がない」「早くして」と言いたくないけれど、つい口にしたくなるのは当然のこと。
でもその言葉は、子どもにとって「食事=楽しくない」と感じさせてしまうこともあります。言葉で自分の状況を伝えられない子どもにとって、無理に食べさせるよりも、安心できる雰囲気の中で繰り返し食べ物に出会うことが好き嫌いを少なくしていくことに効果的です。
今日からできる小さな工夫
忙しい毎日でも実践できるポイントを3つご紹介します。
- 「やりたい」を認める
汚れてもいい服やシートを使い、時間のある日に、食べこぼしOKの日を作る。 - 周りが「おいしい!」と食べる
食べられなくても、これは美味しいのかもしれない。という記憶が残ります。 - できたことに注目する
「モグモグできたね」「スプーン持てたね」と小さな成功を褒める。
これなら今日からでも、子どもと笑顔で向き合えるのではないでしょうか。
働くママに伝えたいこと
2歳の食事は、「栄養をきっちり摂る訓練の場」でも、「食事作法を正しく身につける時期」でもありません。「やりたい気持ち」を受け止める大切な時間です。食べこぼしも、偏食も、成長のプロセスの一部。
「今はこういう時期なんだ」と視点を変えるだけで、イライラが少し和らぎます。
食べ方や、完食よりも、「楽しく一緒に食べられた」という経験こそが、未来につながる食習慣を育てていきます。

まとめ
2歳は「自分でやりたい」と「好き嫌い」が同時に現れる時期。
- 「食べたい=きちんと食べる」ではない
- 好き嫌いは後天的で、環境によって助長されることもある
- 食べこぼしや偏食も、成長の一部であり、喜ばしいこと。
今日からできるのは、「美味しいね」と声をかけたり、「やりたい気持ち」を認めること。
その小さな工夫が、子どもの未来の食習慣と心の豊かさにつながります。 子どもの成長段階を知っておくだけで、毎日の食卓に少し余裕が生まれるのではないでしょうか。